 |
|
| BLOG「芦田の毎日」最新版 | |||
| BLOG「自己ベスト」 | |||
| BLOG「教育」 | |||
| BLOG「家族・子育て論」 | |||
| BLOG「社会・思想」 | |||
| BLOG「政治」 | |||
| BLOG「日常」 | |||
| BLOG「映画」 | |||
| BLOG「商品批評」 | |||
| BLOG「TV・芸能・スポーツ」 | |||
| BLOG「家内の症状報告」 | |||
| BLOG「講演・論文」 | |||
| 掲示板「芦田の毎日」 (旧掲示板「芦田の毎日」) | |||
| 「芦田の毎日」第一期総集編 (2000/10/10〜2001/5/28) [203KB] | |||
| 「芦田の毎日」第二期総集編 (2001/6/12〜2001/12/26) [197KB] | |||
| 「芦田の毎日」第三期総集編 (2002/1/1〜2002/4/13) [186KB] | |||
| 著作 | |||
| 講演・発表 | |||
| 翻訳 | |||
| 論文 | |||
| 外部団体の活動など | |||
| 東京工科専門学校校長の辞 | |||
| その他・雑文 | |||
| 履歴・連絡先 | |||
| 著作 |
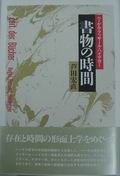 『書物の時間
― ヘーゲル・フッサール・ハイデガー』(366頁:行路社・1989)
『書物の時間
― ヘーゲル・フッサール・ハイデガー』(366頁:行路社・1989)
1.ヘーゲルと書物の時間 ― 序文の現象学
2.an ihm ということ ― ヘーゲルと隠喩
3.表現と意味 ― デリダのフッサール理解について
4.非性の存在論的根源について ― 『存在と時間』論
5.累積について
| 講演・発表 |
1. 「人文系データベース(哲学DB)の現状と開発」
情報知識学会 1993年度 第1回研究報告会
1993年5月22日 於・凸版印刷(東京)
2. 「教育におけるグループ・ウェアとは何か」
1996年 主催:ロータス(株) 於:リーガロイヤル早稲田
3. 「職業教育・情報教育・生涯学習」 ![]()
(財)東京都都私立学校教育振興会主催
生涯学習研修会
1997年11月21日 於・メジカルフレンドビル(東京)
4. 「脱18才を念頭に置いた新たな教育体系」
全国専門学校情報教育協会主催 「マルチメディア教育シンポジウム」
パネルディスカッションパネラー 2000年2月25日 於・ダイヤモンドホテル(東京)
5. 「教育改革の核としての授業改革」
北海道私立専修学校各種学校連合会札幌支部
新年研修会
2001年1月10日 於・札幌グランドパレスホテル
6. 「プロフェッショナルスクールへの取り組み ― リカレント教育とは何か」
中央情報教育研究所
情報化人材育成学科(I類)校研究交流会
2001年1月24日 於・タイム24ビル(東京)
7. 「教育の自己点検・自己評価と授業評価」
全国専門学校情報教育協会・2002年度夏期研修会
2002年8月23日 於・中央工学校軽井沢セミナーハウス
8. 「専門学校と社会人教育について ― コマシラバス思想とは何か」(講演)
広島工業大学専門学校夏期研修会
2002年8月28日 於・広島工業大学沼田校舎(広島市安佐南区)
9. 「テラハウス社会人教育への取り組み」(特別講義)
桜美林大学社会人大学院 学生リクルーティング講座
2002年10月19日 於・桜美林大学社会人大学院新宿校舎(東京都新宿区)
10. 「授業評価とは何か ― 東京工科専門学校の教育改革」(講演)
滋慶学園・定例研修会
2002年11月25日 於・滋慶学園西葛西校舎(東京都江戸川区)
11. 「『自己点検・評価』とは何か」(講演)
「専門学校における自己点検・評価」研修会 全国専門学校情報教育協会
2003年度夏期研修会 2003年8月8日 於・幕張セミナーハウス
12. 「教育改革としての『自己点検・評価』 ― 東京工科専門学校の場合」(講演) ![]()
全国専門学校青年懇話会 第13回経営戦略セミナー
2003年10月9日 於:神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ
13. 「コアコンピタンス形成としての『自己点検・評価』」(講演)
2003年11月15日 於・山口県宇部市・学校法人昇陽学園
(山口医療福祉専門学校、山口情報ビジネス専門学校、山口キャリアデザイン専門学校、
防府福祉医療専門学校)
4校合同研修会
14. 「教育改革と『自己点検・評価』」(講演)
2004年3月6日 「全国専門学校建築教育連絡協議会」西日本支部主催
(於・大阪工業技術専門学校)
15. 「『自己点検・評価』とは何か」(講演)
2004年7月3日 「全国専門学校建築教育連絡協議会」東日本支部主催
(於・読売東京理工専門学校)
16. 「FDの中核としての授業評価」(講演)
2004年8月5日 大学アドミニストレーター研修講座
社団法人日本私立大学連盟主催
(於・東京市ヶ谷 私学会館)
17. 「専門学校の課題、展望、生き残り戦略 - 教育指標の形成をどう行うか」
(講演)
2004年12月7日 社団法人私学経営研究会主催 (於・東京市ヶ谷 私学会館)
18. 「東京工科専門学校の教育改革 ― コマシラバスによる教育マネジメントの現在」(講演) ![]()
2005年2月28日 (株)リコーテクノシステムズ 全国事業部長研修会
(於・リコーテクノシステムズ本社)
19. 「新しい教育評価の試み〜コマシラバスと授業評価指標の形成〜」(講演) ![]()
2005年4月22日 「知的生産の技術」研究会 講演会
(於・霞ヶ関商工会館)
20. 「授業評価と教育改革」(講演)
2005年7月4日 神奈川県立大井高校 教員研修会 (於・神奈川県立大井高校)
| 翻訳 |
1.「私の立場−デリダは答える」(高橋允昭監訳)
雑誌『理想』第618号(1984) 、後に『他者の言語』(法政大学出版局刊 1989)に所収
 2.『還元と贈与』(J-L.マリオン著)
訳者代表 (行路社 1993年9月)
2.『還元と贈与』(J-L.マリオン著)
訳者代表 (行路社 1993年9月)
i.「突破と拡大」
ii.「存在者と現象」
iii.「自我と現存在」
iv.存在の問いか、存在論的差異か
v.存在と領域
vi.無と呼び求め
訳者解説:「存在論から現象学へ」(芦田宏直)
| 論文 |
1.ヘーゲルと存在論の〈端初〉
(早稲田大学大学院人文研究科修士論文 1981年)
ヘーゲル哲学に於ける「存在」と「端初」の問題を、ヘーゲルの著作における〈序文〉の位置づけ、特にヘーゲルが序文は本来著作の本論にとって不要なものだということをそれ自体序文で言い続けたことの意味を探りながら、究明したもの。特にガダマーやリクールなど現代の現象学的解釈学における叙述論(テキスト論)とヘーゲルの『精神現象学』の叙述論とを突き合わせることによってヘーゲルの「端初」論の存在論的な性格を浮き彫りにしたもの。
2.an ihm ということ ― ヘーゲルと隠喩(早稲田大学「文学研究科紀要」別冊11集、1984)
「人間は理性的だ」という場合、この発言は(たとえば動物という「他」の生き物と比較して)「対他」的に言われる場合がある。しかし、この対他性は人間「そのもの」の「他」性でもある。すべての人間が理性的であるとは限らないからだ。ヘーゲルはそのことを、「即自的(an sich)にあるものは、その身の上に(an ihm)もある」という言い方で表現した。この an sich とan ihm との区別と連関は、精神現象学「緒論」での意識の尺度論と論理学(大論理学)の定在論の議論の要をなしている。本稿は、アン・イームと即自との関連と差異を明らかにしながら、ヘーゲル哲学の存在論的な意義を明らかにしたもの。
3.表現と意味 ― デリダのフッサール理解について ![]()
(早稲田大学「フランス文学語学研究」6号 1987)
デリダは、フッサール現象学を「現前性の形而上学」と呼ぶ。それは、フッサール現象学を「直観主義」的な現前主義とみなすからである。特にフッサール『論理学研究』第二研究「表現と意味」における記号論は、記号的な回付なしに「現前」する直観主義的な〈意味〉(表現の意味)を確保するためのもの、つまり、直観の、他の何ものへも回付されない「自己への現前」を確保するためのものとデリダはみなす。デリダは、こういった解釈にしたがって、フッサールとハイデガーとの関係に故意に断絶を作ってしまう。果たして、この解釈は正しいのか。特にハイデガーのフッサール継承に関わって、デリダのフッサール解釈の妥当性を問うた論文。
4.非性の存在論的根源について ― 『存在と時間』論
(『書物の時間』(行路社)所収)
ハイデガーの『存在と時間』における「非」の性格 ― 「不安」の分析から始まり、「負い目」「死」の分析へと展開する ― をその存在論的な観点から究明したもの。この問題の伏線となるのは、『存在と時間』における世界性と自己性との両義的な関係である。『存在と時間』後半で、世界性の議論は潜伏し、むしろ現存在の「全体性」の議論に取って代わられる。現存在の全体性は、死への全体、「責めある」、「非力な」全体として議論されるが、しかし、こういった現存在の自己=非力な全体からする『存在と時間』後半の展開と前半の世界性とはなお断絶があるように思われる。世界性と現存在の自己の非力さとは、果たして同じものなのかどうか、ハイデガー後期の「ケーレ」の問題を意識しつつ議論したもの。
5.言語の意味、あるいは言語と意味について−フッサールの言語−意味論
(『哲学世界』第10号 1987,
早稲田大学大学院文学研究科哲学研究室)
フッサール記号論の特質は、現象学的な意味=直観を「存在するもの」とはみなさず、「アプリオリ」なものとするところにある。この現象学的な先行性(非時間的な、つまり直観的な先行性)が、能記と所記、意義の層と意味の層といった記号学的な区別のすべてに先立っている。この論考は、フッサール現象学の意味論を存在論的な「アプリオリ」の観点から明らかにし、リクールやデリダの現象学的意味論がフッサール解釈としてきわめて問題の多いものであることを明らかにしたもの。
6.哲学と死のデータベース−“電子共同体”とは何か ![]()
(「創文」1992年7月号 創文社)
情報化による文献のフルテキスト化は、個別の著作や個別の著者を越えた汎テキスト性を浮き彫りにする。しかもこの問題は単に著作性の問題にとどまらず、DNAのような人間の記号性そのものを形成するものにも及んでいる。“フルテキスト”化の波が全体的に押し寄せているのが、今日の情報化の根本動向である。この情報化を、近代的な〈主体性〉や〈所有権〉の崩壊として捉え、ポストモダンの予兆と考える一連の動きがある。しかし情報化はむしろ空間や時間の均質化を徹底的に押し進めるという点で、そしてまた人格のゼロ地点としての主体性の基盤が空間や時間の均質性にその地盤を有しているという点で、近代化の極点でもあるということを忘れてはならない。モダンとポストモダンの狭間としての情報化を問題にしたのが本論考。
7.哲学・引用・データベース
(京都短期大学紀要第22巻 1993)
人文系で特にテキストクリティークをその本分(の一部)と見なしている分野(たとえば、歴史学、古典文学、哲学など)の研究にとって、昨今のパソコンの高性能化、インターネットによる国内外の大学の(図書館の)文献解放は、従来の研究方法 ─ またその意味で従来の研究者育成や大学の人材育成における「情報リテラシ」教育の位置づけを根本的に変えるほどの影響力をもっている。この論文では、世界的な規模で急激に進みつつある古典文献のフルテキスト(フル電子文字)化の現状と今後の大学における研究や教育の在り方、その社会的な影響を論じている。
8.存在論から現象学へ−ハイデガー・フッサール・マリオン ![]()
in:『還元と贈与』J-L. マリオン(行路社刊 1993)
フッサール現象学とハイデガー現象学との親近性や対立の問題はどちらの現象学を問題にするにしても避けては通れない主題の一つである。現代フランス現象学の代表的な研究者、ジャン・リュック・マリオンは、この問題を、フッサール『論理学研究』「第六研究」に重点を置くハイデガーの立場と「第二研究」に重きを置くデリダ の立場─ 第二研究に重きを置いて、フッサールとハイデガーとを故意に敵対的な関係に置くデリダの立場 ─ とを対照しながら解明していく。核心的な問題は、現象学と存在論とを親和的な関係と見なすか、敵対的な関係と見なすかということにある。この論考は、存在論と現象学との関係を現象学の最新研究マリオンの諸論文に定位しながら明らかにしたもの。
9.『存在と時間』と世界 ― 世界と他者
(京都短期大学紀要「論集」第23巻 1995)
公刊されている『存在と時間』前半の「世界性」の議論は後半では現存在(の自己)の「全体性」の議論に収斂していき、世界性の議論はほとんど消滅してしまっている。『存在と時間』の概念装置の表舞台の一つ、「世界-内-存在」としての現存在の世界性は、存在(そのもの)の究明を課題とする(初期)ハイデガーにとってどうのように躓きの石となっているのであろうか。「形而上学とは何か」「根拠の本質について」など『存在と時間』直後の論文とのすでにある微妙なズレをたどりながら、ハイデガーにおける存在問題と世界概念との関係を議論したもの。
10.ハイパーテキスト論 ― 情報リテラシについて ![]()
(京都短期大学紀要第24巻 1995)
「情報社会」「インターネット」「情報リテラシ」など、情報化をめぐる社会の変化は指摘するまでもない。むろん大学改革や教育の「生涯学習」化による変化も情報化の一現象である。情報化が社会的な流動性の技術的な基盤だからである。否定的な意味でも肯定的な意味でも情報化の動向と本質を見極めることが今日の高等教育を考える場合の鍵となると思われる。本稿は、インターネットを通じて大衆的に普及し始めた「ハイパーテキスト」「ハイパーリンク」 ─ 源流はテッド・ネルソンが1960年代に提案した「ハイパーテキスト」論 ─ の思想に今日の情報化の特質と教育改革の道筋を見いだしたもの。
11.フレーム問題と世界 ― 人工知能・哲学・ハイデガー ![]()
(東京立正女子短期大学紀要, 第23号, 東京立正女子短期大学, 1996)
ウイナーのサイバネティクス以来、機械もまたオープンシステム(環境世界の変化に開放的に対応するシステム)でありうることが明らかになってきた。人間もまたあるいは人間こそがオープンシステムであることを考えれば、ウイナーのこの確信は機械と人間の対立、あるいは人間とその他の動物との(キリスト教的な)対立を解消させる衝撃的なものであった(この対立の解消が「人工知能」派の思想的な論拠になっている)。しかし、人間の環境性(世界性)とウイナーのサイバネティクスが想定するオープンシステムとは同じ構造なのだろうか。コンピュータのサイバネティクス的な人間性はどこまで人間的なのかをハイデガーの世界概念と対照させながら明らかにしたもの。
12.言語の近代主義について ― フッサールと意味の隠喩
(東京立正女子短期大学紀要第26号、1997)
デリダは、記号(能記)としての言語とそれが指示する意味されるもの(所記)の区別を参照しながら、所記の純然たる現前(特に彼が「超越論的所記の自己への現前」と呼んだもの)を保持しようとする目論見や企ての全体を西洋形而上学の、「現前性の形而上学」としての特徴とみなした。デリダによれば、しかしそういった超越論的な所記こそが、能記としての能記が反復的に自己差異化する(彼が「差延」と呼んだもの)、むしろ能記の「効果」なのだ、ということになる。こういったソシュールから出発した能記/所記の記号論的な対立からする「現前性」の議論は、形而上学の根本体制を正しく評価すること ─ 肯定的な意味でも、否定的な意味でも ─ にどれだけ資するのか。この論考は、ソシュール的な記号論的差異とフッサール現象学における意味論を対照させ、「現前性」の評価が記号学的な差異にとどまらない射程を含んでいることを明らかにしたもの。
13.カントの〈始元〉論 ― 『純粋理性批判』における「生起しない」原因性について
(東京立正女子短期大学紀要 第27号
東京立正女子短期大学 1998)
カントの『純粋理性批判』における「生起しない」原因性について、特にハイデガーの存在論的なカント解釈を参照しながら、超越論的統覚の「自己触発」との関連を議論したもの。
14.免許・資格教育と大学改革 ![]()
(リクルート 「カレッジマネジメント」 第96号 1999年6月)
15.高等教育における授業改革とは何か ― 教育における目標と評価
(東京都専修学校各種学校協会 平成13年度紀要論文)
16.社会人教育市場をどう取り込むか
(これまで大学、専門学校が取り込めなかった6つの理由) ![]()
(リクルート「カレッジマネジメント」連載記事:117号)
17.高等教育における授業評価とは何か ― 授業評価の停滞
(平成14年度財団法人東京都私立学校教育振興会・研究助成金論文)
| 外部団体の活動など |
○ 全国専門学校情報教育協会幹事 (2000年〜)
( http://www.invite.gr.jp )
○ インターネット教育協議会理事 (2000年〜)
( http://www.vic.gr.jp/~vic_admin/ )
○ 2000年度 労働省「IT化に対応した職業能力開発研究会」委員
( http://www.ashidahironao.info/trees/trees.cgi?log=&v=185&e=msg&lp=185&st=0 )
○ 2003年度 経済産業省「産業界から見た大学の人材育成評価に関する調査研究」 委員
( http://www.ashidahironao.info/jboard/read.cgi?num=212 )
○2004年度 文科省「特色ある大学教育支援プログラム」第3審査部会委員
( http://www.juaa.or.jp/sien-program/frame-sienprogram.html )
| 東京工科専門学校校長の辞 |
1. 校長式辞
● 東京工科専門学校グループ入学式式辞・卒業式式辞
(01) 2002年度入学式式辞 ― 「インターネット時代の社会と学校」 ![]()
(02) 2002年度度卒業式式辞 ― 「学歴主義と終身雇用の崩壊」 ![]()
(03) 2003年度入学式式辞 ― 「社会に出るというのはどういうことか」 ![]()
(04) 2003年度卒業式式辞 ― 「単純な仕事にこそ差異は生じる」 ![]()
(05) 2004年度入学式式辞 ― 「若いときにしか勉強はできない」 ![]()
2. 授業評価
(01) 校長の仕事01: なぜ授業がつまらないのか。 2002.11.8 ![]()
(02) 校長の仕事02: “個性”と教育 2002.11.11 ![]()
(03) 校長の仕事03: 「ヒューマニズム」について 2002.11.28 ![]()
(04) 校長の仕事04: CPUは、〈モノ〉か? 2003.5.6 ![]()
(05) 校長の仕事05: なぜ、出典を明記しない? 2003.7.11 ![]()
(06) 校長の仕事06: まだまだ授業がよくない 2003.8.26 ![]()
(07) 校長の仕事07: 授業を記録することの意義 2003.9.4 ![]()
(08) 校長の仕事08: 教科書内の図版の説明 2003.9.19 ![]()
(09) 校長の仕事09: 作品批評という授業スタイル 2003.9.23 ![]()
(10) 校長の仕事10: 〈粗利〉と〈純利〉 2003.9.25 ![]()
(11) 校長の仕事11: 思考力と製図力 2003.9.29 ![]()
(12) 校長の仕事12: 〈講評〉というデザイン教育の問題点 2004.2.2 ![]()
(13) 校長の仕事13: わが学園の〈授業評価〉大公開 2004.5.20 ![]()
(14) 校長の仕事14: わが学園の〈授業評価〉続編 2004.5.23 ![]()
(15) 校長の仕事15: わが学園祭を評価する 2004.10.30 ![]()
(16) 校長の仕事16: 「美の根源は自然の中にある」 2004.11.9 ![]()
(17) 校長の仕事17: ユニバーサルデザインとは何か(1) 2004.12.16 ![]()
(18) 校長の仕事18: 建築と構造力学 2005.7.13 ![]()
3. テラハウスキャリア開発研究所所長の辞 2002.4.8 ![]()
ユーザーコンピューティング宣言(旧労働省「IT化に対応した職業能力開発委員会」発表論文)
| その他・雑文 |
* 文中のリンク先が存在しない(消滅)している場合があります。
2. 携帯電話、ザウルス、レッツノートミニ ― モバイル・コンピューティングについて 1998.4 ![]()
4. カシオペアファイバ+6ギガハードディスク換装騒動顛末記 1999.6 ![]()
| 履歴・連絡先 |
芦田宏直(アシダヒロナオ) 1954年8月12日 京都府生まれ
早稲田大学大学院後期博士課程修了(哲学、現代思想専攻)
法政大学講師(倫理学)、立正大学講師(哲学)、京都短期大学講師(社会学)、東京立正女子短期大学(哲学・ドイツ語)、学校法人小山学園・テラハウスICAキャリア開発研究所所長を経て、現在、学校法人小山学園東京工科専門学校校長、学校法人小山学園理事。
著作: 『書物の時間』(行路社 1988)、翻訳『還元と贈与』(行路社 1994)。
現住所: 〒157-0062 東京都世田谷区南烏山2-31-31 蘆花公園プレスティージュ808号室
メール : ashida@tera-house.ac.jp
| 「芦田の毎日」最新版 (旧版) |